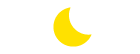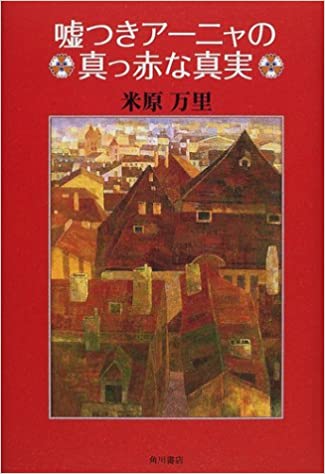
プラハ、ブカレスト、ベオグラード、サラエボと東欧の街の名前が出てくる。名前ぐらいは知っているけれど、それらの街の位置関係となるとよくわからない。まして、それらの街の様子がどんなで、どんな人たちがどんな家に住み、どんな暮らしをしているかなどほとんど知らない。そういう意味で遠い国々だ。著者は1950年生まれ。冷戦さなかの59年~64年、小4から中2にかけて在プラハ・ソビエト学校に学ぶという経歴を持つ。父親が日本共産党からプラハにあったある機関へ派遣されていたそうだ。本書はそのとき仲良しだった三人の友だちの消息を追って、90年代に現地を訪ねたときの話である。68年プラハの春、89年冷戦終結、再燃したバルカン半島の民族紛争、NATOによる空爆・・、東欧には激動のあらしが吹き荒れた。とぼしい手がかりをたよりになんとか旧友との再会を果たすが、三人のその後の人生はそれぞれ波乱に満ちたものだった。奇しくも20世紀という時代を生々しく描き出した作品になっている。ノンフィクションだが、まるで小説のように話の展開は劇的だ。