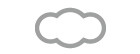なちかつ
図書館WEB
おすすめ本棚のコーナーなのに、読んで「?」の本をとりあげてよいものか。なにせこの本は、心やさしく忘れっぽくきげんのいいリスや、知っていること考えることが多すぎて頭の重みに耐えかねているアリ、樹の上のリスの家にやって来てやたらと樹から落ちたがるゾウ、そのほかイカ、タコ、カブトムシなど癖のある変わり者たちが次から次へと登場してくるのである。そして一つ一つの短い話は「?」と思う間に終わる。しかし、この本は本屋大賞翻訳小説部門堂々の2位だ。評価は高い。「?」の自分のほうが悪いのだろうか。なにはともあれ、このような本は速く読んではいけません。ゆったりした気持ちのときに、ゆったりと読めば「!」と心に来るものがあるかもしれません。
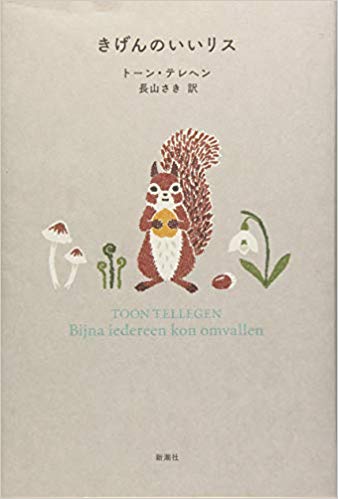
- 詳細
- 作成者:NCL編集部
- カテゴリー: おすすめ本棚
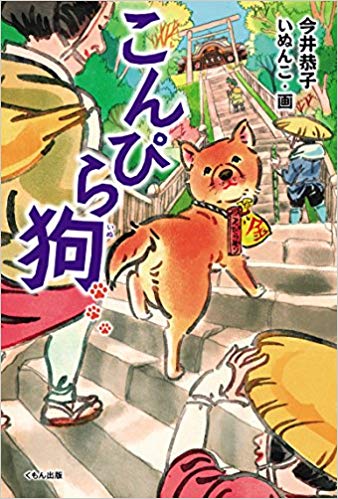
江戸時代も終わりに近い頃、主人に代わって長い旅をし、金比羅宮にお参りに出された狗(いぬ)があったという。当時の人たちは狗を代参させた人の心を思って、道々その狗を大事にしたそうだ。この本は江戸から讃岐までの往復を成しとげたこんぴら狗ムツキの冒険物語。フィクションだが綿密な取材で迫真の物語に仕上がっている。
- 詳細
- 作成者:NCL編集部
- カテゴリー: おすすめ本棚
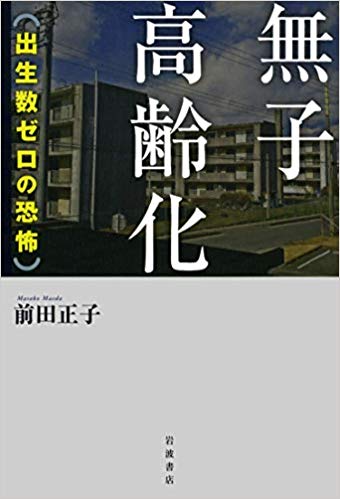
高齢化とか少子化とか、言葉だけはずっと以前から言われていてだれもが知っていたことだが、それがどんな社会かいよいよ現実味を帯びて見え始めてきた現代、もはや取り返しがつかない時期に入ってしまっていることに愕然とする。有効な対策がとられないままに、生産年齢人口の減少と高齢化率の上昇はセットでやって来た。想像力の欠如だけではないだろう。国民も政治もそのときどきの課題にとらわれて、この数十年間無策だった。楽観的に待っていた90年代後半から2000年代にかけての第3次ベビーブームはとうとう来なかった。
- 詳細
- 作成者:NCL編集部
- カテゴリー: おすすめ本棚